住宅ローン
はじめての住宅ローン
住宅ローンの金利とリスク
そこで、ここでは住宅ローンに関する基本的な情報をご紹介します。
変動金利型
- 金利の変化
- お借入れ後の金利は、毎年2回(4月1日・10月1日)見直し、原則として7月と翌年1月の約定返済分から適用いたします。
- 返済額の変更
- 金利に変動があった場合でも約5年間(10月1日を1回経過するごとに1年が経過したものとみなします)は、ご返済額を変えずに、ご返済額の中での元金部分と利息部分の内訳で調整(利息分が優先)いたします。そして5年ごとの金利見直しに合わせて、ご返済額の見直しをいたします。
ただし、金利が大幅に上昇した場合でも、新ご返済額は前回ご返済額の1.25倍(例4万円→5万円)を上限といたします。 - 固定金利型への変更
- 変動金利型でのお借入れ期間中は、いつでも固定金利型に変更できます。
ただし、ご返済中に固定金利型へ切り替えられた場合、それ以降引き下げ金利は適用されません。
リスク
変動金利型は、金利変動による急激な返済負担増加を緩和する目的で、約5年間はご返済額が一定であり、見直し後のご返済額が増加する場合でも変更前の毎回のご返済額の1.25倍までと決まっています。しかし、その場合でも金利は半年に1度見直しがあることに注意が必要です。
ご返済額の内訳(利息および元金)は、半年毎の金利変更によってその割合が変わりますが、ご返済額は約5年間変わりません。そのため、金利が上がるとご返済額に占める利息の割合が増加するのです。(下図<A>参照)
さらに大きく金利が上がると、利息がご返済額を上回ることになり、返済しても元金は減らず、ご返済額を超えた利息分を後に繰り延べて支払う必要が生じます。これを未払利息といいます(下図<B>参照)
なお、最終のご返済額の変更以降、金利の変更に伴い、最終期日に未払利息および元金の一部が残る場合、最終期日に一括してご返済いただくこととなります。
また、約5年毎の見直しでご返済額が増加する場合にも、変更前のご返済額の1.25倍が上限(下図<C>、<D>参照)なので、大きく金利が上がると、支払うべき利息が変更後のご返済額を超えて未払利息が発生する可能性があります。(下図<D>参照)
以上は金利が上がった場合のリスクの説明ですが、金利が下がった場合はご返済額に占める元金の割合が増えることとなり、元金のご返済が進むことになります。
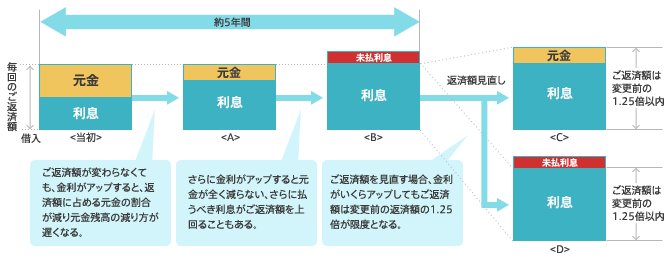
固定金利型
将来の金利上昇によるご負担増を避けることができます。
- 固定金利期間、経過後の金利
- 固定金利期間経過後は、その時点の適用金利による固定金利型か変動金利型のいずれかをお客さまが自由に選択できます。
同時に、選択された金利に応じてご返済額の見直しをいたします。なお、固定金利期間経過時までに特段のお申し出がない場合は、変動金利型になります。
リスク
固定金利特約期間終了時には、お借り入れ利率の変更に伴い、ご返済額が変更となりますが、その際はご返済額の変動幅に上限設定(変動金利型のような1.25倍制限)がありません。このため、固定金利特約期間終了後は、金利変動により毎回のご返済額が大幅に増加(または減少)することもあります。
上手な活用法として、金利が今後どのように変わっていくのか予測しながら、固定金利と変動金利をうまく選択していくという活用法があるでしょう。ただし、固定金利特約期間中は、金利タイプの変更ができないうえ、固定金利特約期間終了後に金利が大きく上昇し、大きくご返済額が増加するリスクがあることを忘れてはいけません。
お電話からのご相談・お問い合わせ
福岡中央銀行
営業推進部
![]() 0120-675-430
0120-675-430
※受付時間:9:00〜17:00(但し、銀行休業日は除きます)
※上記のフリーダイヤルがご利用いただけない場合
092-751-4667
